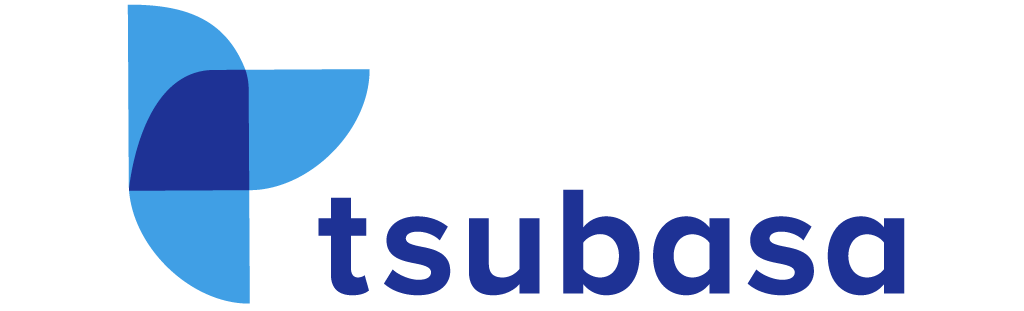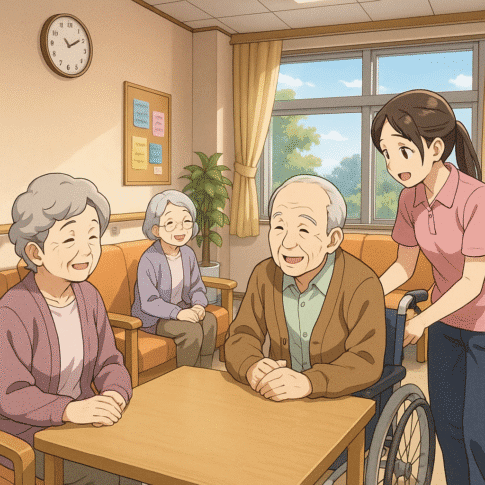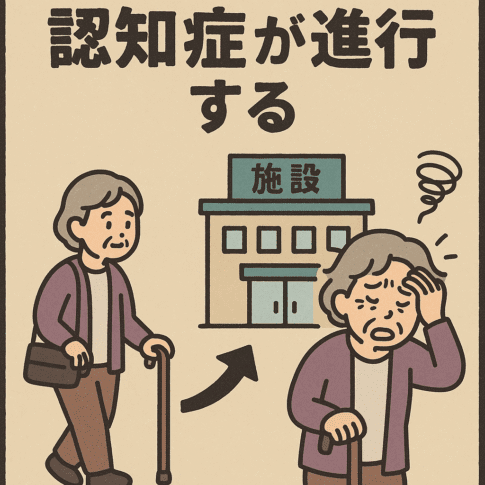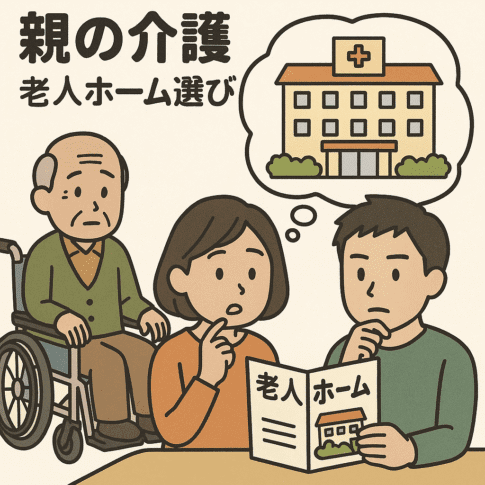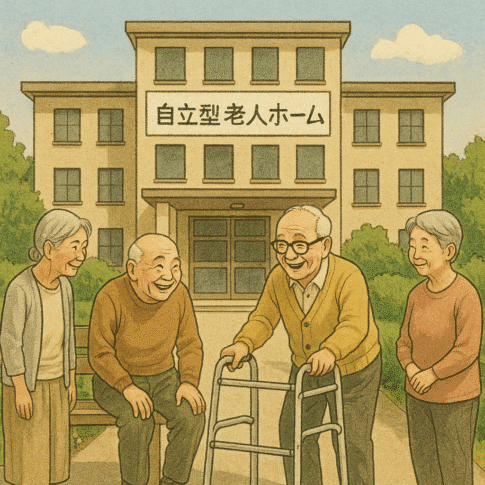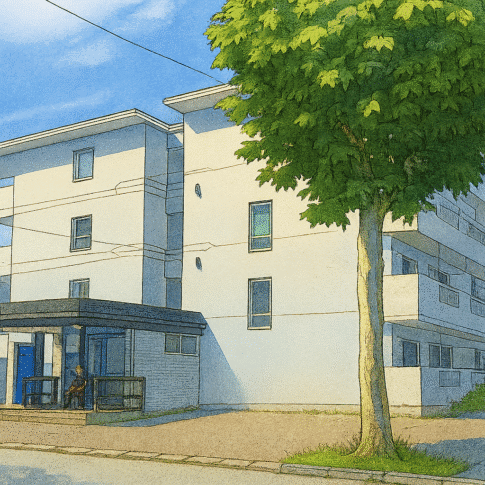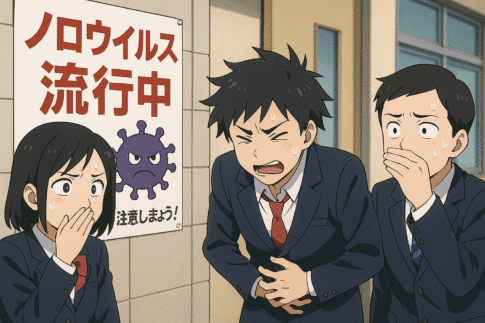共同通信(2024年12月28日)によると、2024年度上半期(4~9月)の生活保護申請件数は、前年同期比2.8%増の13万3,274件に上り、コロナ禍以前の2019年同期と比べても16.8%も増加しています(詳細は共同通信の該当記事を御覧ください。)。こうしたデータを背景に、世間では「社会保障財源の圧迫」を理由に生活保護を批判する声や、「生活保護は働きもしないで楽をしている」という偏見が見られます。しかし、高齢者介護の現場をはじめ、実際に受給者と接する現場の印象として、決してそうしたイメージばかりではないのが現状です。
とりわけ、「高齢者の生活保護」受給に至る経緯には、多様なケースが存在します。長引く物価高や年金の不足、新型コロナウイルスに伴う支援の縮小だけでなく、交通事故や大病、離婚などの予測不能な事態によって、生活基盤が一気に崩れてしまう人も少なくありません。「自分には関係ない」と思っていても、人生で何が起こるかは分からず、誰にでも起こり得る現実問題といえるのです。
Contents
なぜ「高齢者の生活保護」受給が増えているのか
物価高や支援縮小の影響
近年の物価高は、高齢者の家計を圧迫しています。食費や光熱費などの日常的な支出がかさむうえ、加齢に伴う医療費・介護費用の負担が大きくのしかかるからです。さらに、コロナ禍で行われていた一時的な支援策が縮小や終了を迎え、すでに低所得状態にあった高齢者がより厳しい生活へ追い込まれることも起きています。
賃上げや経済回復の動きが一部で見られるものの、非正規雇用や年金だけに頼る高齢者にその恩恵が十分に届いていない現実があります。そのため「頼れるものは生活保護しかない」という状況に至るケースが少なくありません。
交通事故や大病、離婚による生活基盤の喪失
高齢者介護の現場などで見聞きする生活保護受給者の実態として、「もとは普通に働いていたが、交通事故に遭い体が不自由になった」「大病を患って仕事を続けられなくなった」「離婚によって収入も住まいも失った」というケースが多くあります。
働く意思や能力があっても突然のトラブルや病気がきっかけで収入源を断たれ、やむを得ず生活保護を受給するに至る――こうした境遇は、自分や家族が明日にでも経験する可能性があるかもしれません。
生活保護は本当に「楽」なのか?高齢者介護の現場が見る現実
決してぜいたくな暮らしではない
「生活保護受給者は働かずに楽な生活をしている」というイメージが、実情をどれほど反映しているかは疑問です。受給額は、最低限の生活を維持するために算定されるものです。多くの高齢者介護の現場で働く人々は、受給者が“ぜいたく”どころか「ギリギリの生活」を送っている姿を目の当たりにしています。
確かに、不正受給や働く意欲のないまま保護を続ける例がゼロではありません。しかし、それは統計上ごく一部の事例にとどまると言われています。大多数は、辛うじて生活を立て直すために必要な支援を受けるだけです。
高齢者にとってのセーフティネットの意義
高齢になると、再就職のハードルが格段に高くなります。体力や健康面での制約に加え、採用市場でも若年層を優先する企業が多いため、フルタイムの安定収入を得ることは難しくなります。ましてや、交通事故や大病をきっかけに職を失った方が再び働き口を見つけるのは至難の業です。離婚によって生活基盤を失う女性や、高齢の独居男性なども同様に、経済的・精神的なダメージから回復するには相応の時間と支援が必要です。
このような場合、社会保障としての生活保護が最後の砦(セーフティネット)となります。「誰でも、どんな理由でも受給できる」というイメージではなく、むしろ「ギリギリまで耐えざるを得なかった人」が駆け込み、最小限の生活を確保するための制度なのです。
高齢者の生活保護を巡る今後の課題と視点
社会全体が「自分事」として考える必要性
生活保護の受給増加に伴い、「財源を圧迫する」「国民の負担が増える」といった批判が起こるのは当然です。しかし、高齢者が置かれた厳しい状況を考えれば、誰もが受給リスクを抱えているという視点が大切です。働き盛りの時期に順調でも、交通事故や大病、離婚といった不測の事態が重なれば、誰でも生活保護に頼らざるを得ない状況になる可能性があるのです。
医療・介護・雇用支援を横断する包括的対策
今後は、生活保護制度そのものの見直しと同時に、医療・介護・雇用の支援策が相互に連携する包括的なアプローチが求められます。高齢者が安心して治療や介護を受けながら、働ける意欲や機会があればそれをサポートする体制を整える――こうした取り組みを進めることで、生活保護を受給する前段階での支援や、受給からの早期自立を目指すことが可能となります。
まとめ―「他人事ではない」高齢者の生活保護
「高齢者の生活保護」が増加している背景には、長引く物価高や支援縮小だけでなく、交通事故や大病、離婚などの予測不能な出来事が起こりやすい高齢期の現実があります。「生活保護は楽だ」というステレオタイプな見方もありますが、実際には決してぜいたくとは言えない条件下で暮らしている高齢者が多数です。
誰しもが働けなくなる瞬間や、生活を支えていたパートナーや家族との関係が途絶えるリスクを抱えています。だからこそ、生活保護制度は社会全体で支えるべき重要なセーフティネットなのです。「自分には関係ない」と考えず、高齢者だけでなく現役世代も含めたすべての人が、自分事として制度や社会保障のあり方を見直していく必要があります。