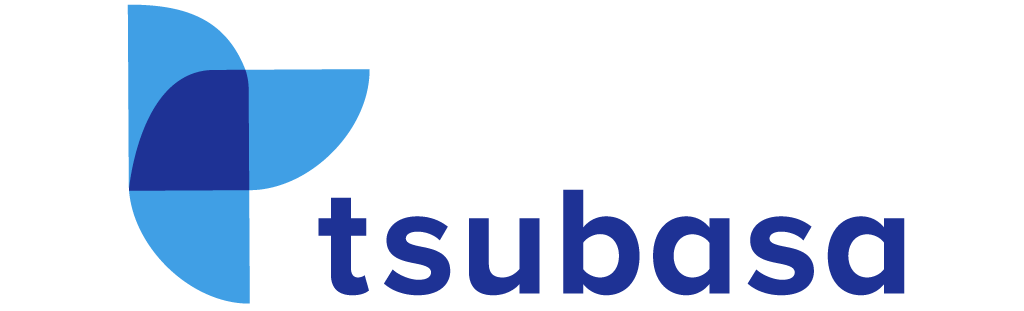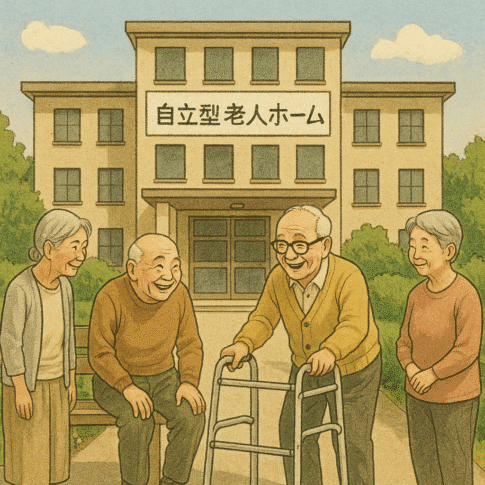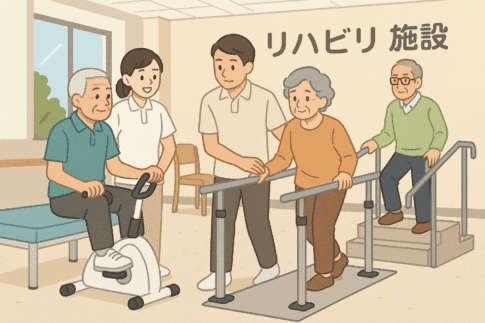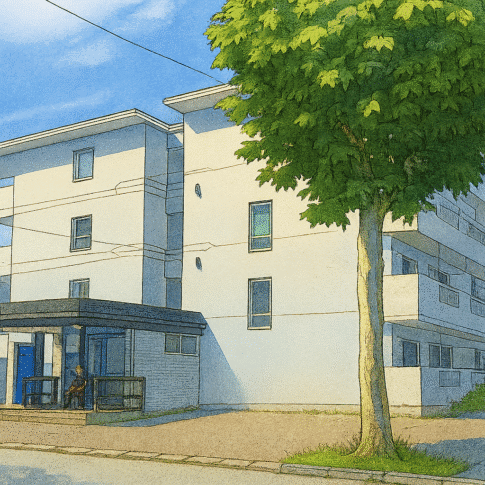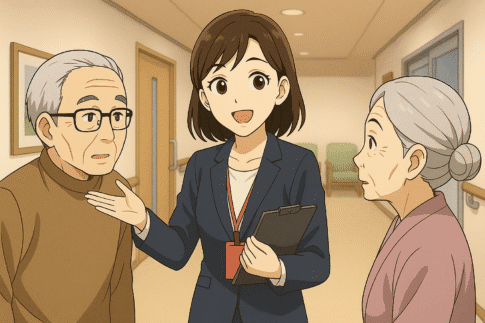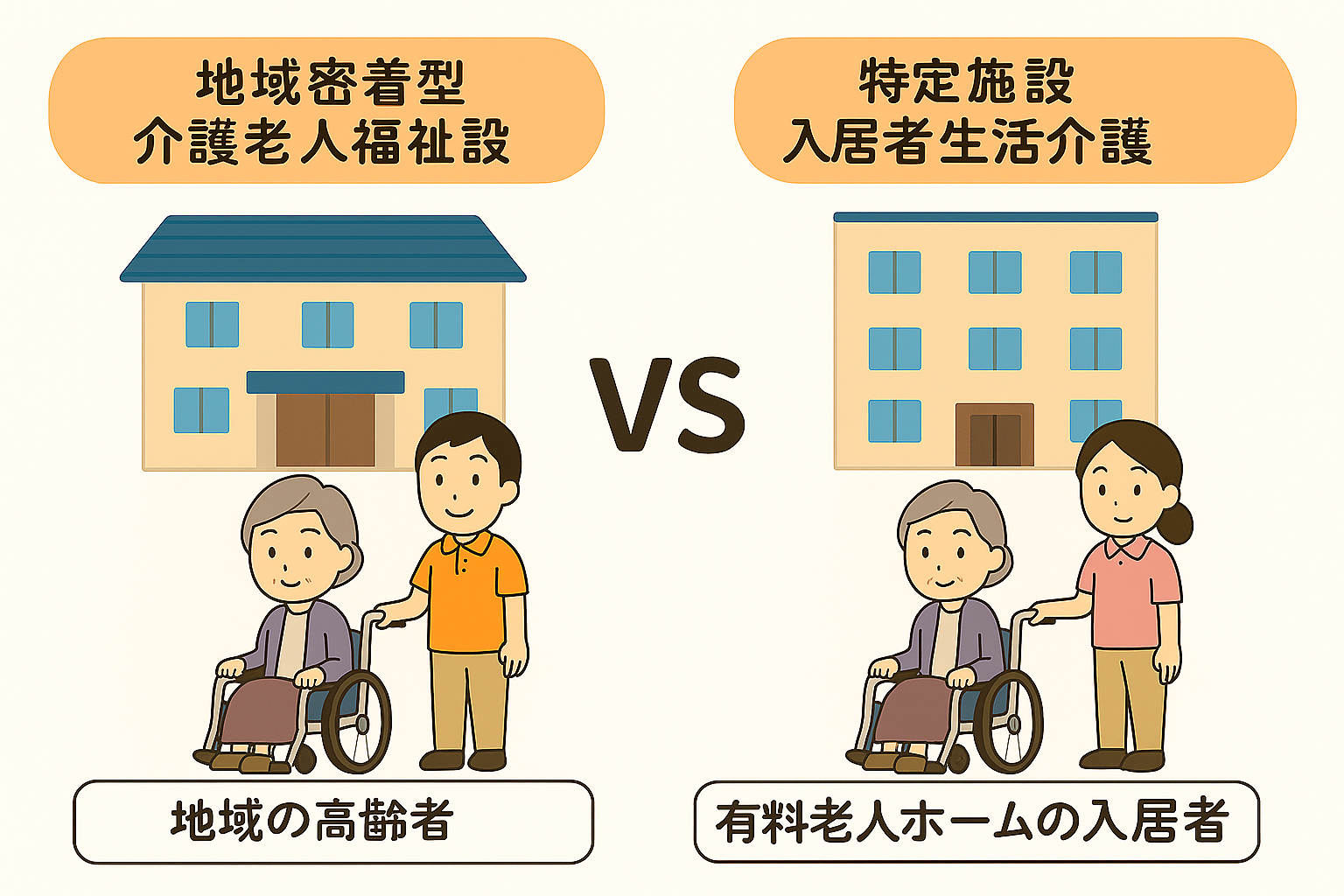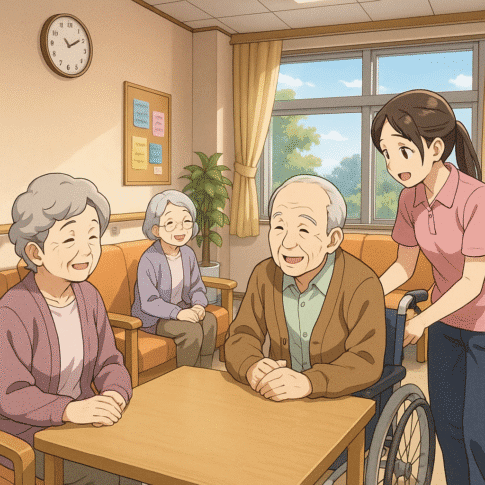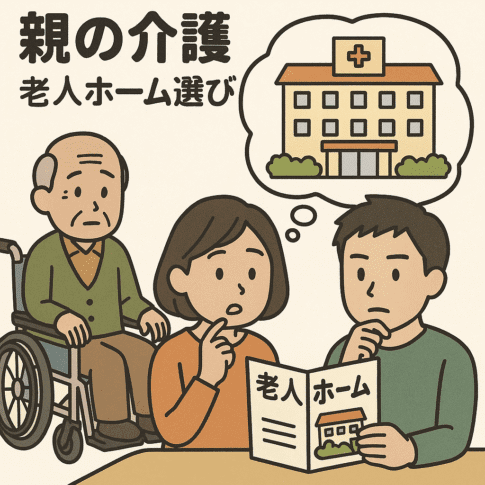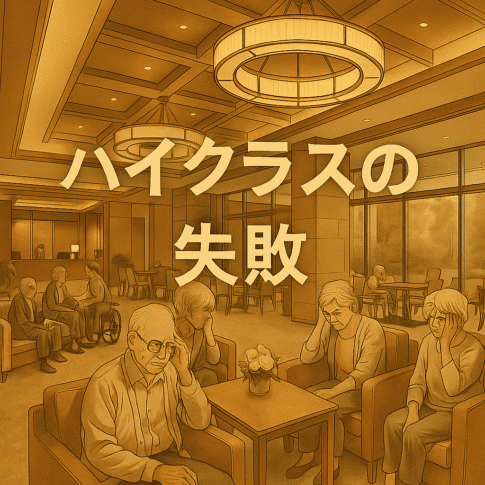Contents
コロナ対策交付金の実態:朝日新聞の調査が示す、交付金の疑問点
コロナ対策交付金とは何か?
新型コロナウイルスの感染拡大に直面し、日本政府は2020年に地方自治体を支援するため「地方創生臨時交付金」としてコロナ対策交付金を設立しました。総額18.3兆円という巨額の予算が割り当てられたこの交付金は、地方自治体が独自の判断で使えるとされています。
朝日新聞の詳細な調査手法
朝日新聞はこの交付金の使われ方を分析するため、内閣府が公開している自治体ごとの事業計画を対象に、統計分析ソフトを用いて調査を行いました。2023年10月までに提出された約23万件の事業計画が分析の対象となりました。
交付金が投じられた意外な事業
調査結果からは、キャンプ場のWiFi整備、トイレの洋式化、レンタル用自転車の購入など、アウトドア関連の事業や花火イベントへの資金投入が明らかになりました。これらの事業は、直接的なコロナ対策とは異なるものの、地域振興や住民の憩いの場としての位置付けを強調しています。
地方自治体の挑戦か、コロナ対策の見落としか
これらの事業が地方自治体の新しい挑戦として評価される一方で、コロナ対策としての直接的な影響は疑問視されています。特に、公衆の集まるイベントへの資金投入は、コロナ感染拡大のリスクを無視しているのではないかとの指摘もあります。
交付金の使用に対する社会的な疑問
交付金の使途に関しては、地方自治体の自由な判断に委ねられているものの、その使われ方には社会的な疑問が残ります。コロナ対策として最も効果的な方法で資金が使われているのか、また、今後同様の状況に直面した際の対応策として、これらの事例がどのような教訓を提供するのか、継続的な監視と議論が必要でしょう。