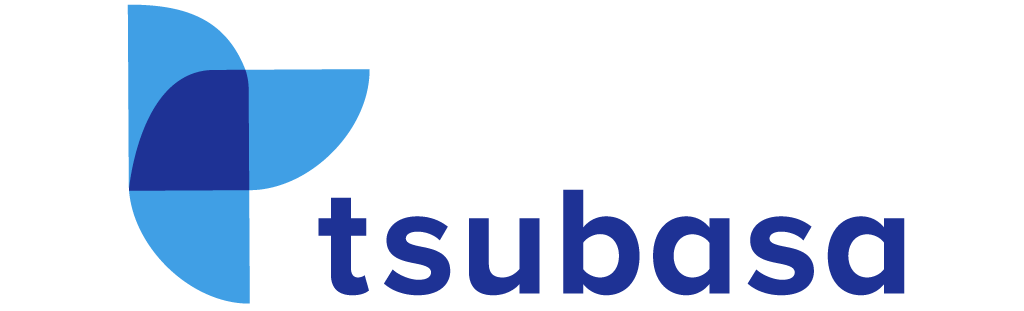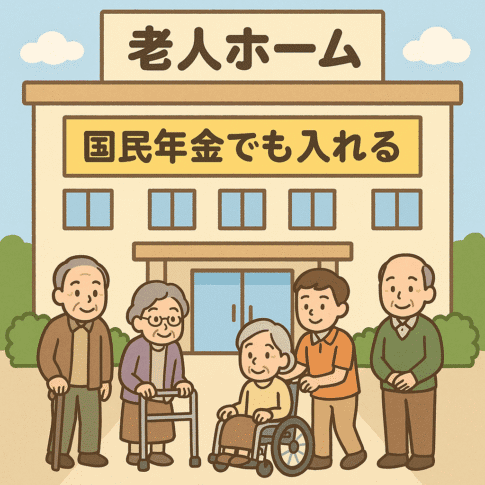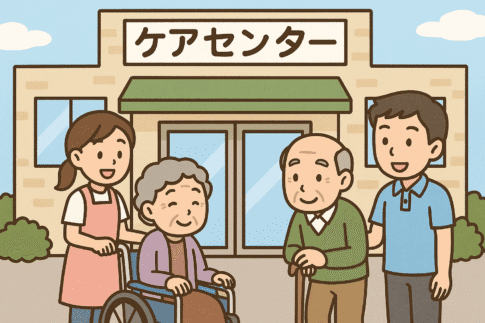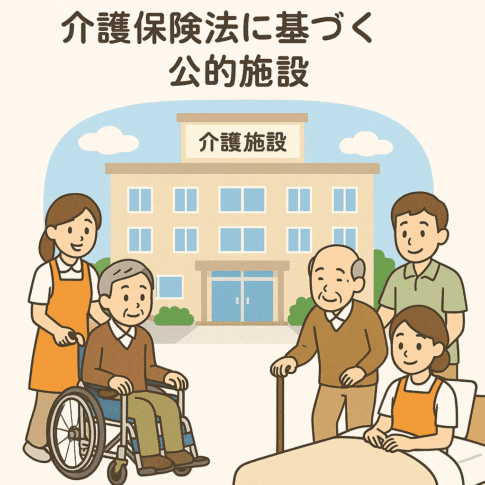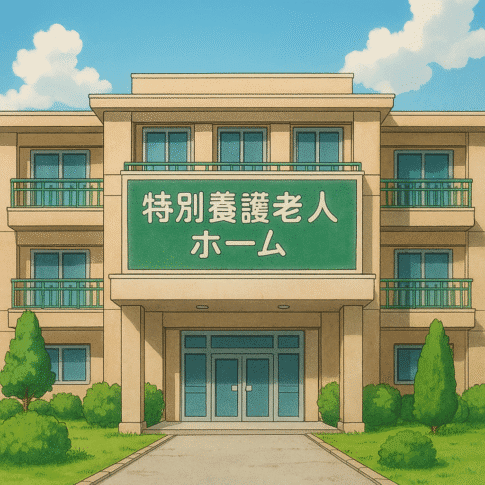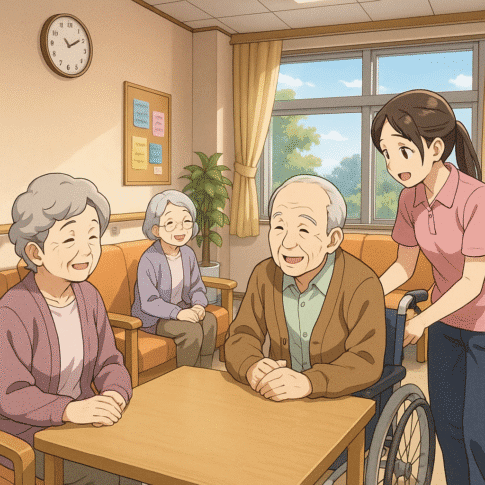高齢化社会とデフレが進行する日本において、コンビニエンスストアは今や生活に欠かせないインフラとして機能しています。特に地方都市では交通アクセスが悪く、身近な買い物場所が限られているため、コンビニの存在は文字通り“命綱”になっているといっても過言ではありません。そんな中、セブン-イレブンが展開する「うれしい値!」は、高齢者や価格感度の高い層から強い支持を得ており、今後もますます注目されるでしょう。本記事では、高齢化社会とデフレの視点に加え、地方都市での実情を踏まえながら、「うれしい値!」の価値や狙いを詳しく解説します。このコラムは食品新聞(2025年1月5日)の内容をもとに作成されています。
Contents
地方都市とコンビニのライフライン化
地方都市では、公共交通機関の本数が少なく、スーパーマーケットなどの大規模店舗が近くにないケースも珍しくありません。車を持っていない高齢者や若い世代にとっては、徒歩数分で必要な物を手に入れられるコンビニは貴重な存在です。実際、「毎日の食事を用意するためにコンビニで買い物をする」という高齢者は少なくありません。こうした現状から、コンビニは生活必需品を提供するだけでなく、住民同士や店員とのコミュニケーションの場としても重要な役割を果たしています。
高齢化社会とデフレの背景
日本は世界屈指の速さで高齢化が進行し、少子化による働き手不足や経済成長の停滞が続いています。デフレ傾向が長く続いたことで、消費者の価格感度はますます高まり、年金収入など限られた予算のなかでいかに日々の生活をやりくりするかが大きな課題となっています。
- 高齢化の進展:65歳以上の割合が増加。年金暮らしの方が4000万人を超える社会に
- デフレの長期化:高齢化により物価が上がりにくく、消費者が“安さ”を重視
このような状況下で、コンビニ側は単なる“便利さ”だけでなく、品質と価格の両方を満たす商品を求められるようになりました。
「うれしい値!」導入の経緯と目的
セブン-イレブン・ジャパン(以下、SEJ)の永松文彦社長は、2024年9月から本格展開した「うれしい値!」について、「物価高と生活防衛意識の高まりを受け、来店頻度を上げるきっかけにしたい」という狙いを語っています。
- 対象品目数:300品まで拡大
- メディア露出:TVCMなども投入して認知度を向上
こうした取り組みは、商品ベンダーとの情報共有を密に行いながら、高品質かつ手ごろな価格を実現しようという姿勢の表れです。また、高齢者から若年層まで幅広く支持を得るため、“安かろう悪かろう”ではないラインナップづくりにも注力している点が特徴です。
高齢者との結び付き:株式会社つばさメディカルグループの経験
地方都市や郊外部で介護サービスを提供している株式会社つばさメディカルグループが担当するエリアでも、多くの高齢者が最寄りのコンビニを日常的に利用しています。足の不自由な高齢者でも自宅から歩いて行ける距離にコンビニがあるため、
- 買い物難民の解消
- 店員とのコミュニティ形成
- 生活リズムの維持
といった効果が生まれています。「高齢化社会とデフレ」がコンビニに新しいビジネスモデルを提供しているように感じます。特に、高齢者が店員さんと顔見知りになり、世間話をすることで生きがいや安心感を得るケースも多く、ケアマネージャーが介護士が毎日巡回しなくても店員やそこに集まってくる高齢者のコミュニティが見守りの役割を果たしているのは事実です。これは医療・介護の現場にも好影響をもたらし、コンビニが「調子が悪そうなときに店員さんが声をかけてくれる」などの見守り機能を果たすという不思議な役割を担っています。また、認知症の高齢者が自宅や施設から抜け出し、徘徊をした際でも、経験的にかコンビニに立ち入ることがあり、コンビニから連絡がくるということも稀ではありますが、あることです。
新規顧客を取り込む鍵:20代男性と女性の増加
SEJによると、「うれしい値!」導入以降、20代男性と女性を中心とした新規顧客が増えているといいます。高齢者だけでなく、若者にとっても「より安く、より美味しい」商品は魅力的です。
- 若者の価格感度:将来の不安から節約志向が高まる
- 女性層の健康志向:栄養バランスや手軽さを重視
こうしたニーズに応えることで、これまでスーパーマーケットやドラッグストアを利用していた層もコンビニに取り込むことができ、「近所の日常使いの店」としての認知がますます高まっています。
価格帯別「松竹梅」戦略の重要性
セブン-イレブンでは、「うれしい値!」を価格帯別“松竹梅”戦略の“梅”に位置付けています。
- 松:高品質・高付加価値の商品(プレミアムラインなど)
- 竹:スタンダード商品(一般的な価格帯)
- 梅:手ごろな価格帯の「うれしい値!」
この明確な区分によって、顧客は自分の予算やニーズに合った商品を選びやすくなります。高齢化社会とデフレが続くなか、一部の高価格商品だけをそろえる戦略ではターゲットを狭めてしまいがちですが、あえて価格の幅を広げることで、多様化する消費者ニーズに対応しているわけです。
高齢化社会とデフレの罠:高価格戦略とインバウンド需要のジレンマ
コンビニ各社が一時期、高価格帯の商品開発を強化していた背景には、「訪日外国人(インバウンド)」の増加があります。観光客を対象にした高品質・高価格の商品は確かに売上増につながる可能性がありますが、年金で生活する高齢者が多い地域では必ずしも最適解ではありません。
- インバウンド狙い:高い客単価が期待できる
- 地域密着:日々の生活に必要な商品を手ごろな価格で提供
特に地方都市では、観光客よりも地元住民の利用頻度が圧倒的に高いため、高齢者をはじめとする地元の人々が無理なく利用できる価格帯こそが、コンビニの真価を引き出す重要な戦略となっているのです。
地域フェアやコミュニティ形成の相乗効果
セブン-イレブンの永松社長は、「安さ」だけでなく、地域フェアなどのイベントによる“ワクワク感”の創出も重視しています。高齢化社会とデフレの影響を受けながらも、生活を楽しみたいという消費者の気持ちに応えるため、各地域の特産品を使った限定商品や季節キャンペーンを実施するのです。
- 地域限定メニューの発売:地元の味を気軽に楽しめる
- コミュニティの活性化:店員や常連客との会話が増える
こうした施策は、高齢者から若年層まで幅広い顧客の来店理由を増やすだけでなく、コミュニティ形成に寄与し、ひいては地域全体の活性化にも繋がります。
今後の展望:社会ニーズと経済性の両立
高齢化社会とデフレの進行が止まらない以上、コンビニにはこれまで以上に地域社会を支える重要なインフラとしての役割が求められていくでしょう。「うれしい値!」のように、生活防衛意識の強い層でも利用しやすい価格設定と高品質を両立させることは、コンビニの競争力を高める上で大きなアドバンテージとなります。
さらに、地方都市で特に重要視されるのは、コミュニティスペースとしての機能です。株式会社つばさメディカルグループの介護現場のように、高齢者が店員と顔なじみになり、見守りや声かけなどの小さなつながりから安心感を得る事例は今後ますます増えるでしょう。一方、インバウンドを意識した高価格商品路線だけに偏ると、地元住民の経済的・心理的ハードルが上がり、利用頻度が下がるリスクもあります。
そのため、「松竹梅」戦略で幅広い価格帯をそろえつつ、地域フェアやイベントでワクワク感を演出し、誰もが気軽に立ち寄れる店舗づくりを行うことが今後の鍵となるはずです。コンビニは単なる物販の場を超えて、地域コミュニティの絆を紡ぎ、高齢化社会とデフレに立ち向かう重要なステークホルダーへと進化していくことでしょう。
まとめ:
高齢化社会とデフレが進む日本で、地方都市の住民にとってコンビニエンスストアはますます欠かせない存在となっています。セブン-イレブンの「うれしい値!」は、年金生活者や若年層の生活防衛意識に応えつつ、地域に密着し、コミュニティを形成する大きな役割を担いつつあると言えます。インバウンド向けの高価格戦略も一定の成果が期待できますが、地方では地元の高齢者層をはじめ、日常使いの顧客が中心です。価格帯を多様化し、地域の声を反映した商品やイベントを展開することで、**“近所の日常使いの店”**としての存在感はさらに高まっていくことでしょう。
今後もコンビニがどのように地域コミュニティを支え、高齢化社会とデフレを乗り越えていくのか。その取り組みは、単なるビジネス戦略にとどまらず、日本社会全体の持続可能性を左右する重要なテーマといえます。セブン-イレブンだけでなく、他のコンビニチェーンにとっても「うれしい値!」のような価格戦略と地域密着施策は、これからの時代を乗り切るための大きなヒントになるでしょう。