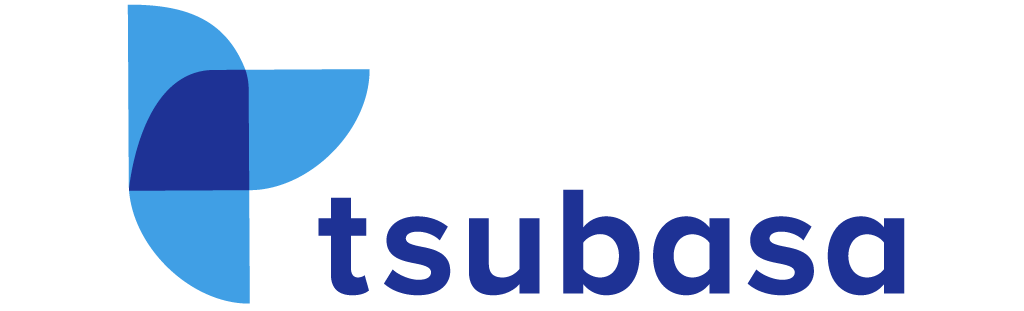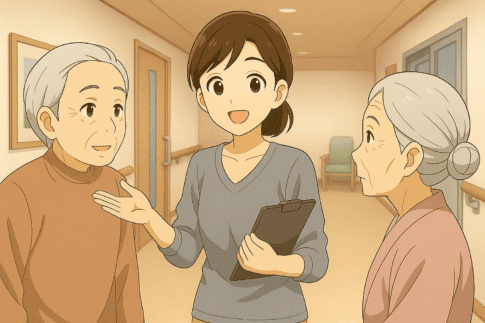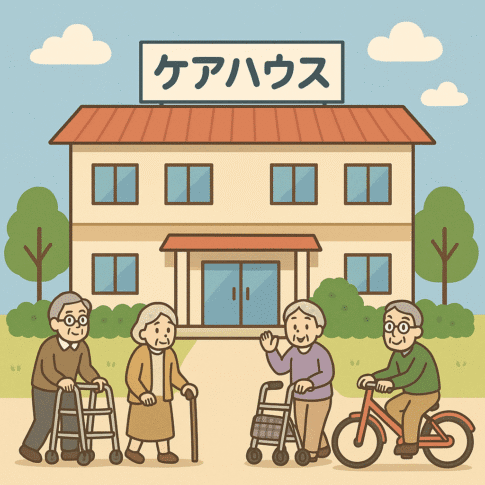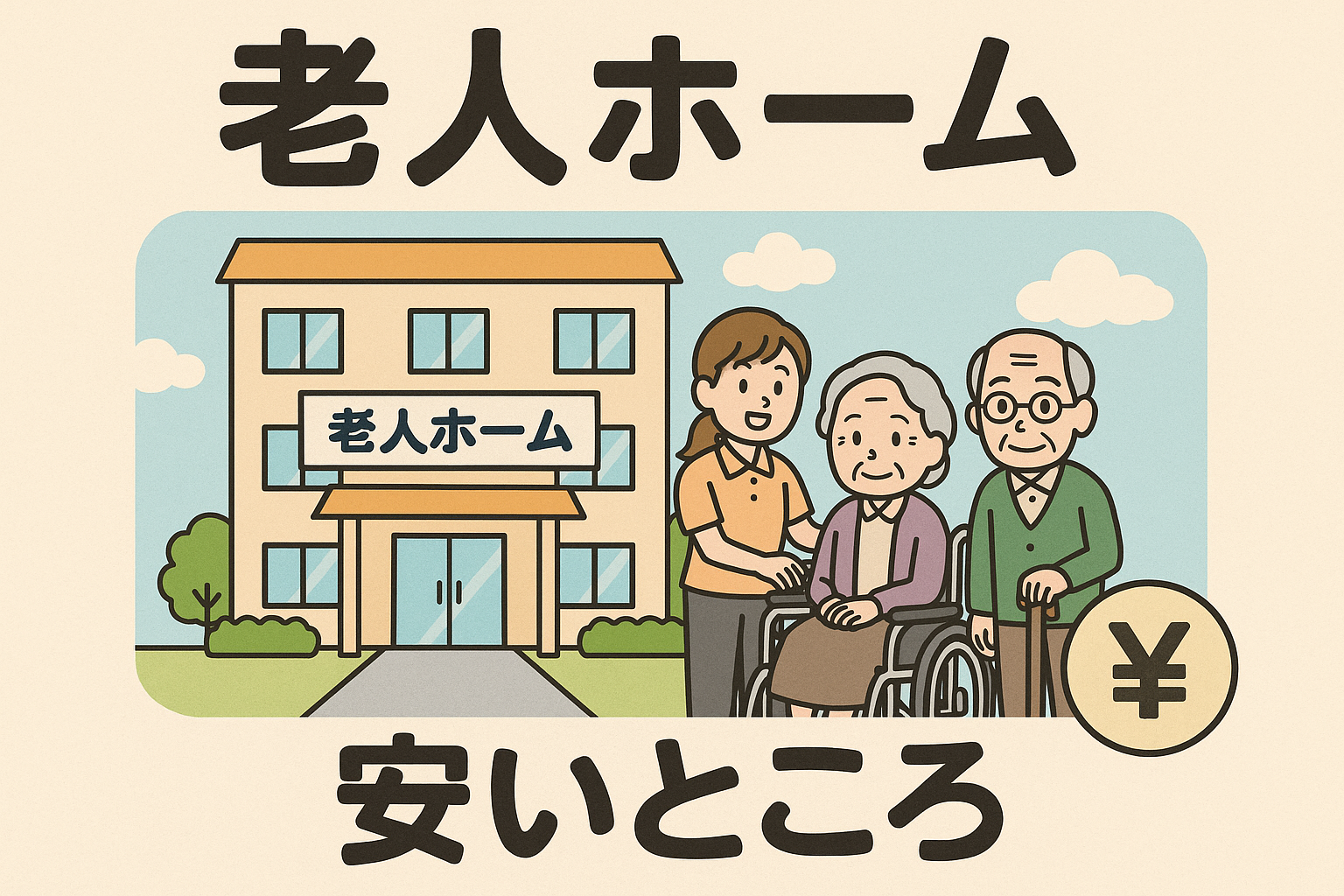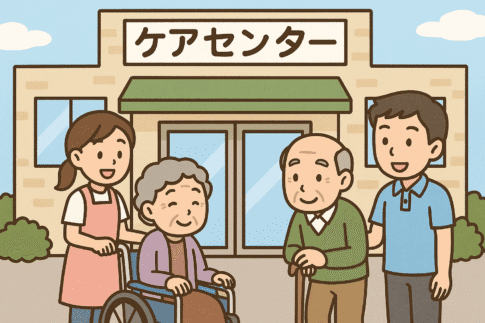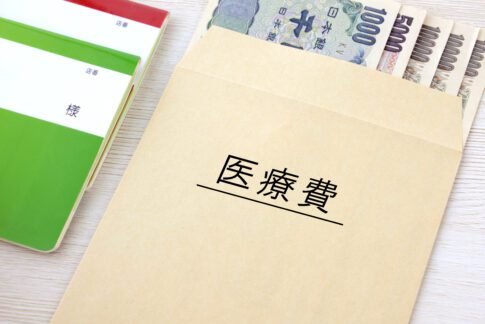札幌市では、インフルエンザが猛威を振るい、救急搬送が「30人待ち」になるほど医療が逼迫しています。さらに、搬送に4時間かかるケースもあるため、市民にとっては深刻な問題です。
当社(つばさメディカルグループ)は、札幌市内で介護施設、訪問看護事業所を運営しており、冬場に感染者が出るたびに人手不足の中で対応に追われてきました。本記事では、高齢者と肺炎のリスクを中心に、この逼迫が生じる背景を掘り下げつつ、介護現場の視点から国や行政への提言をまとめます。医療・介護が直面する課題を理解し、私たち一人ひとりが適切な対策を取るきっかけになれば幸いです。本記事は北海道新聞(2025年1月18日)の記事を参考に作成しています。
Contents
札幌市の救急搬送が逼迫する背景
冬場に重なる感染症
冬の札幌は、インフルエンザ、新型コロナウイルス、マイコプラズマ肺炎などが同時に流行しやすい環境です。特にインフルエンザの患者数が急増すると、発熱外来や救急外来が混み合い、患者が次々と救急車を呼ぶため、医療機関の受け入れ先が足りなくなります。
当社の施設でも、この時期に利用者が発熱すると、コロナ・インフルエンザ・その他の呼吸器系感染症など多角的に疑わなければならないため、職員の対応負荷が一気に高まります。複数の感染症が重なり合うのが、札幌の冬の特有のつらさだと感じています。
救急要請の集中
年末年始は多くの医療機関が休診となり、休日当番医に患者が集中します。軽症でも「高熱で動けない」という理由で119番する人が増えると、隊員や車両の数が追いつかなくなるのは当然です。それでも札幌市の救急対応は非常に迅速かつ的確でいつも頭が下がる思いです。施設運営においては救急隊員との連携が極めて重要になっています。
なお、運良く病院に到着しても、検査や診療を受けるまでに長時間待つ状況が続くため、私たち現場の人間は「本当に救急搬送をすべきかどうか」を常に頭の片隅で考えているのが実情です。
高齢者と肺炎の重症化リスク
高齢者はインフルエンザをはじめとする感染症が引き金となり、肺炎へ進行しやすい傾向があります。肺炎が重症化すると入院が必要になり、救急搬送も避けられません。多くの人が軽症でも搬送を呼ぶ中で、本当に重症化した高齢者が救急車を確保できない恐れがあります。
この「優先度の逆転」は、介護施設でも頻繁に問題視されます。私たちが普段から重症リスクの高い利用者を把握していても、救急に連絡してから受け入れ先が決まるまで時間がかかり、状態の悪化が進むケースを何度か見てきました。
肺炎に関しては、高齢者の死因の上位になるほど深刻なもので、実際、介護の現場の感覚でも一緒です。とにかく肺炎を防ぐために、衛生状態を確保したり、デイサービスなどでの口腔ケアを重視して予防に焦点を当てて対応しています。
高齢者と肺炎:命に関わる理由
インフルエンザとの相互作用
高齢者と肺炎のつながりは、単独の感染症よりも相互作用が深刻です。インフルエンザに感染して体力が落ちているところに肺炎が重なると、一気に重症化する可能性があります。免疫力が低い高齢者ほど、こうした二次感染を避ける努力が必要です。
症状が出にくい高齢者
高齢者は発熱しにくかったり、倦怠感だけで終わる場合があり、周囲が肺炎に気づくのが遅れることがあります。当社の施設でも、わずかに呼吸が浅いと感じるだけで、後から肺炎と診断されるケースがありました。
こうした早期発見の難しさが、高齢者における肺炎のリスクをさらに高めます。毎日の健康チェックはもちろん、少しでも「いつもと違う」と感じたら即受診を検討する態勢を整えなければならないと痛感しています。
医療の逼迫を加速させる要因
肺炎で入院が必要になる患者が増えると、病床も救急車も埋まっていきます。結果として救急要請へのレスポンスが遅れ、別の重症者に対応できない――この悪循環が生まれてしまうのです。
介護施設は医療行為を行う場ではないため、どれだけ迅速に病院へつなぐかが鍵になります。しかし、すでに病院がいっぱいだと、搬送先が見つかるまで待機せざるを得ず、職員はもどかしさと緊張感のなかで利用者を看守り続けることになります。
札幌の冬を乗り切るための基本的な対策
手洗い・うがいの徹底
帰宅後や外出後は、石けんを使った十分な手洗いと、喉の奥までしっかりうがいを行いましょう。基本中の基本ですが、流行期は特に重要です。
マスクの正しい着用
鼻と口をしっかり覆い、隙間がないように着用することが大切です。外出時や人が集まる場所でのマスク使用を習慣にすると、飛沫感染のリスクを下げられます。
ワクチン活用
高齢者は、インフルエンザワクチンと合わせて肺炎球菌ワクチンの接種も検討してください。これにより重症化リスクを大幅に減らせる可能性があります。
適度な運動と休養
体力が衰えると、感染症からの回復力も落ちてしまいます。散歩などの軽い運動と十分な睡眠を心がけましょう。
栄養バランスの確保
ビタミンやタンパク質を中心にバランスの取れた食事が、免疫力を高める基本になります。高齢者は食欲が落ちやすいため、少量ずつでも栄養価の高いものを摂る工夫が必要です。
救急要請の適正利用:本当に必要かを見極める
軽症の場合の選択肢
高熱や咳で苦しくても、歩行が可能で意識もしっかりしているなら、タクシーや自家用車を利用して直接病院へ行くほうが早い場合が多いです。施設では救急要請を出す前に毎日のADLを把握し、早い段階で通院同行を行い、早期に措置をとっています。
重症化が疑われる場合は迷わず119番
呼吸困難や意識障害、胸の痛みなど深刻な症状がある場合は、ためらわずに救急車を呼んでください。高齢者ほど病状が急変しやすいため、早期の行動が命を救う鍵になります。
かかりつけ医・地域連携の活用
症状の軽重を判断しづらい場合、まずかかりつけ医や地域の医療相談窓口に電話相談する方法があります。早い段階で適切な受診先を指示してもらえれば、不要な救急要請を減らすことに貢献できます。
介護現場の視点:介護現場で感じる矛盾と課題
実際介護の現場からの視点からの本件に関する意見や課題を書いてみたいと思います。
感染症発生時の極端な人手不足
当社の介護施設では、職員一人ひとりが複数の利用者を担当しています。札幌ではインバウンドで人材が取られることも起因してか、介護職員の採用は難しくなっており、人員に余裕のないシフトが組まれています。一度、インフルエンザなどの感染症が出ると、隔離措置や清掃・消毒の強化が必要になり、普段の業務に加えて相当な労力を費やします。国が制定した残業規制などもあり、どうしようもない状態に陥ります。人命と法律に従う残業のどちらを優先すればよいのか。
しかも、職員自身が感染してしまえばシフトを埋めることすら難しくなり、負の連鎖が止まらなくなるのです。このような逼迫状態は、北海道の冬には毎年のように訪れます。
介護報酬の問題
国は介護報酬をインフレに合わせて引き上げるどころか、訪問介護の報酬を削減するなどの動きを続けています。施設の集中した訪問介護体制は儲かっているからというのが理由のようです。しかしながら、このような緊急時の人手不足状態は考慮されていないようです。消費税などで社会保障財源が増収になっているはずなのに、介護保険の削減が進む矛盾には疑問を禁じ得ません。
介護現場に十分な財源が配分されなければ、結果として医療全体がさらに圧迫されます。高齢者の重症化や医療費の膨張は、すぐに社会問題化するのに、その対策が後手に回っているのは大きな課題です。
現役世代への影響
多くの現役世代は、親の介護に時間を割かなければなりません。介護費用が十分に補助されないと、在宅や施設を問わず、どちらにしても家族の負担が大きくなります。
さらに、介護現場の逼迫が続けば、誰もがいずれ利用者や家族としてこの現実と向き合うことになるでしょう。介護報酬や制度の改善は「高齢者の問題」だけではなく、「明日の自分や家族」の問題でもあるのです。行き当たりばったりの対策で、外国人技能実習生で補完するという対策なのかもしれませんが、正直、外国人の指導教育まで施設で請け負うというのは、特に札幌のような地方都市で現実的なのか、冷静な検証が必要です。
国と行政への提言:冬の札幌を見据えた具体策
介護報酬の再検討
冬季の感染症リスクを踏まえ、介護施設や訪問介護が継続的に運営できるよう、報酬体系を見直す必要があります。現場の声を集め、柔軟な改定を行うことで、医療圏全体の負担を軽減できます。せめて、冬季だけでも加算をいれるなど。
緊急時の人材シフト支援
感染症が発生した施設への応援スタッフ派遣や、オンコール体制の充実を図る仕組みが求められます。一時的な追加人員や臨時予算を確保できるようにしておけば、逼迫を最小限に抑えられるでしょう。訪問看護事業所に加算を設けて、オンコール体制を拡充させるという手段もあります。
地域包括ケアシステムの充実
かかりつけ医、訪問看護、福祉サービスなどが連携する地域包括ケアを強化すれば、在宅高齢者の急変リスクを早期にキャッチしやすくなります。結果として救急搬送や入院の増大を抑制できるはずです。特に訪問看護の利用は医療の専門家でもある看護師が対応に当たるので効果は大きいです。地域包括ケアにおいて看護師は大きな役割を担えると考えています。
冬季医療計画の整備
札幌の冬は雪や寒さ、路面状況によって移動も容易ではありません。こうした特有の環境要因に加え、感染症流行が予測できるのであれば、自治体は早い段階から医療機関・介護施設と連携し、受け入れ態勢や物資確保を共同で進めるべきです。
まとめ
札幌市で深刻化している救急搬送の逼迫は、複数の感染症が同時流行する冬季特有の要因が大きく影響しています。特に高齢者と肺炎のリスクは密接であり、一旦重症化すると医療・介護の現場に大きな負担がかかります。
介護施設を運営する立場から、国の介護報酬削減や支援の不足が、結果的に医療逼迫を招いていると痛感しています。高齢者を適切にケアするための財源を確保し、地域包括ケアシステムを充実させることは、最終的に現役世代を含む全員の負担を減らす道でもあるのです。
感染を予防する個人の努力と、介護現場への投資・制度改善が両輪となって機能すれば、厳しい札幌の冬の医療事情は、きっと変えていけるはずです。今後も医療・介護の現場と国や自治体が共に連携し、安心して暮らせる地域を目指すことが介護現場の大半の方の願いのような気がします。