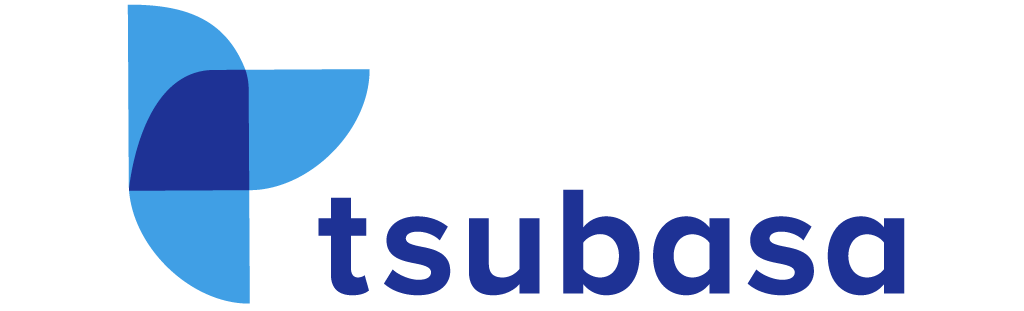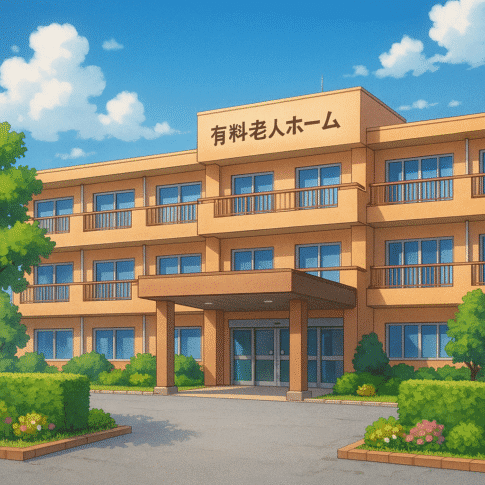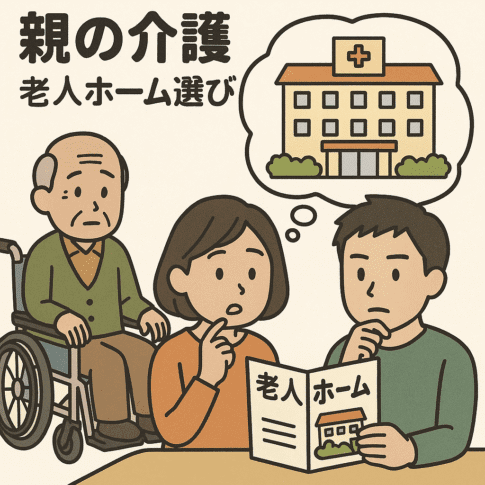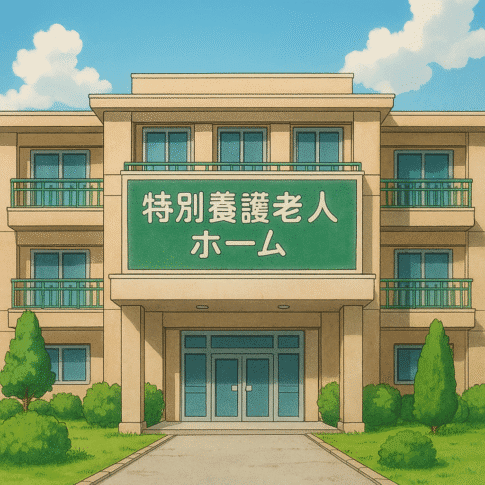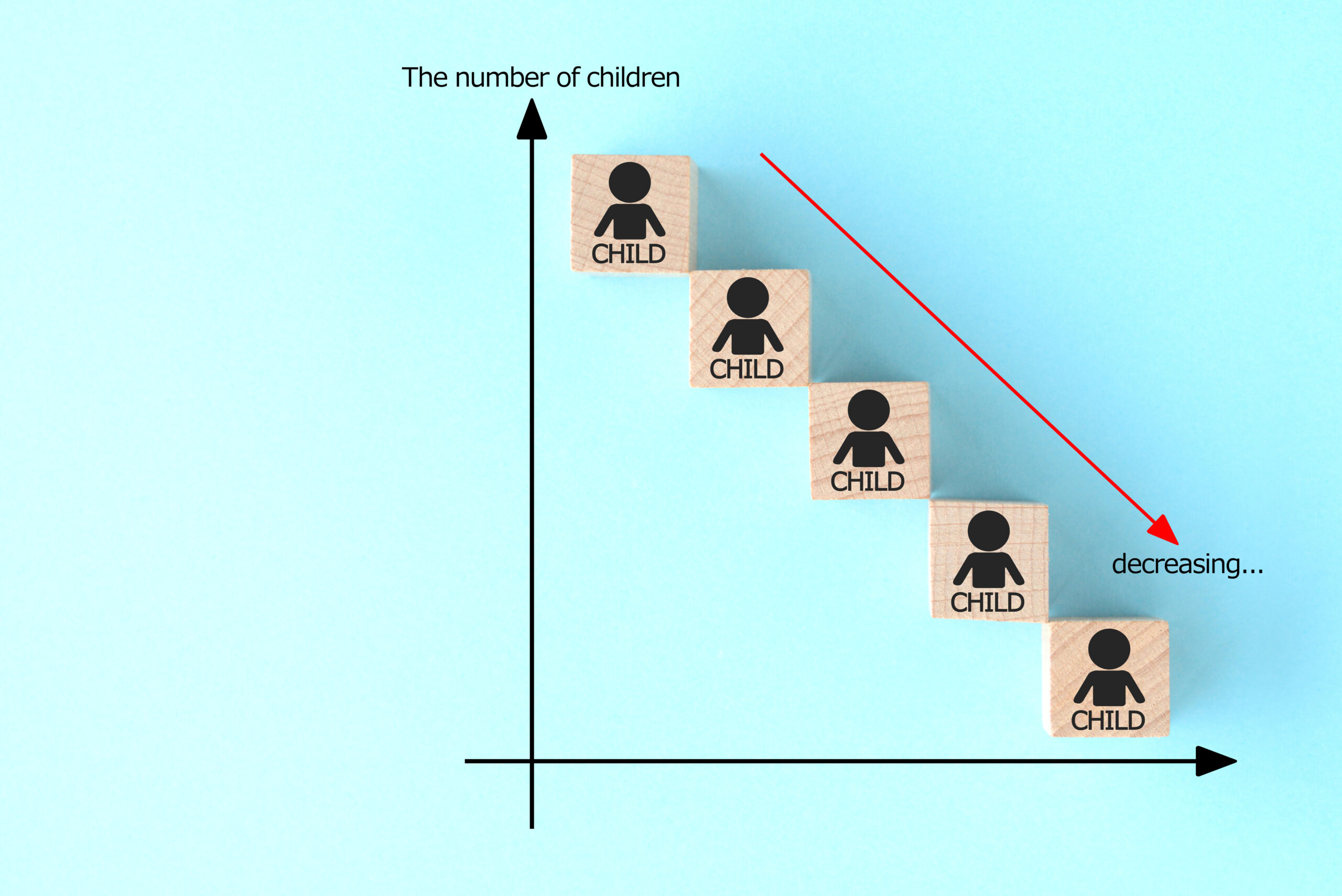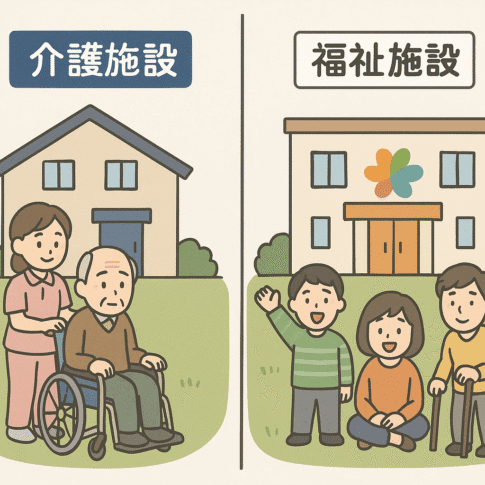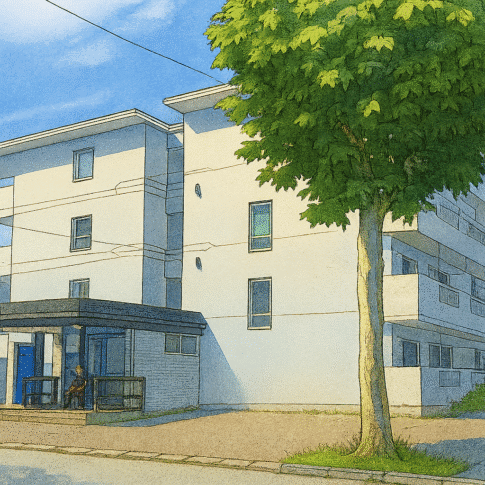2024年、医療機関(病院・診療所・歯科医院)における倒産と休廃業・解散の件数が、ともに過去最多を更新。特に「診療所」と「歯科医院」の増加が顕著で、今後の医療体制にも影響を与えそうです。
本記事では、主な要因や背景、そして「高齢化と病院」をめぐる課題に迫ります。さらに、地方医療の存続を支える新たな取り組み事例についてもご紹介します。本記事は帝国データバンク(2025年1月22日)の記事を参考に作成しています。
Contents
倒産64件、休廃業・解散722件の衝撃
2024年は、医療機関経営事業者の倒産件数が64件に達し、最多だった2009年(52件)を大きく更新しました。内訳は病院が6件、診療所が31件、歯科医院が27件。
さらに休廃業・解散は722件にもおよび、こちらも過去最多を記録。特に診療所の数が大きく増えています。
歯科医院と診療所の倒産が急増
倒産件数を業態別に見ると、歯科医院が27件、診療所が31件で過去最多です。コロナ禍の影響により受診者が減り、経営が圧迫されたことが一因です。
また、設備更新や人材への支出が重く、経営難に陥る施設が増加しています。コロナ補助金削減と資材高騰、融資返済が重なり、経営負担が急増しています。
高齢化と病院:後継者不足という大きな壁
「高齢化と病院経営の逼迫」は全国的な問題です。診療所においては、70歳以上の経営者が過半数を占め、後継者を確保できないケースが急増しています。
日本医師会の調査によると、診療所の半数以上が「後継者候補はいない」と回答。医師の高齢化が進むにつれ、急に休廃業へ追い込まれる状況も見られます。特に地域医療を担う診療所が閉鎖されると、地元住民の生活にも大きな影響が生じます。
休廃業・解散が増える背景
2024年の休廃業・解散件数722件のうち、587件が診療所でした。実に全体の81.3%を占めます。これらの施設は、経営者の高齢化や後継者の不在が主な原因となっています。高齢化と病院経営は密接に関係していると言えます。
また、診療所の数が病院や歯科医院に比べて圧倒的に多いのも特徴です。医療の高度化や患者ニーズの変化に対応できず、更新が遅れた施設が淘汰されている面もあります。
最大負債額は「アリシアクリニック」を展開する法人
2024年の最大負債案件は、美実会(負債72億9500万円)です。一般社団法人八桜会(51億7500万円)と合わせ、多数の債権者が存在し大きな話題となりました。
また、高橋デンタルオフィス(19億円)は、インプラント治療などで多額の前払い金返還訴訟に発展。こうしたトラブルが経営を圧迫し、倒産へと至っています。大きな負債を抱える事例は一部ですが、経営の綻びが加速するケースが増えています。
地方医療を支える新しい取り組み:高齢化と病院の運営承継
外部資本の積極的活用
当社では特に地方の病院の運営を支援するために、不動産ファンドを設立する予定です。個人経営の病院では、どうしても倒産回避が困難です。後継者不足で倒産しないよう医療の提供(ソフト)面における代替の可能化が必要です。インフラ面で安定的な運営をサポートし、ソフト面(運営)を必要に応じて置き換えていくことで、長期的に病院の存続を支えたいと考えています。外部資本による安定的な経営基盤の確保により解決する可能性があります。
運営の流動性を高める必要性
特に地方医療を支えるうえでは経営のチェーン化が重要です。多施設がネットワークを形成することで、コスト削減や人材確保の効率化ができます。各病院の診療科目や設備の役割分担を進め、地域で安心して受診できる環境づくりを目指します。
今後の見通しと課題
2023年度の医療費は約47兆3000億円で過去最高を更新しました。しかし、収入の減少に苦しむ医療機関は少なくありません。受診者が減り、経営体力も縮小。その結果、設備投資や人材確保がままならず、さらなる患者離れを招くという悪循環に陥るケースも増えています。
倒産や休廃業が引き続き高水準で推移すると予想される2025年以降は、より一層の対策が必要です。特に「高齢化と病院運営の逼迫」という問題については、後継者の確保と経営環境の見直しが急務となります。
まとめ
2024年は医療機関の倒産と休廃業の数字が過去最多となりました。その背景には、新型コロナの影響による受診控えや補助金の縮小、経営者の高齢化、そして後継者不足など多くの要因があります。
今後は地方医療の再編とチェーン化、ファンドによる経営サポートなど、新しい形態が求められるでしょう。高齢化と病院経営に関する問題はこれからも深刻化する可能性があります。持続的な医療体制を築くためには、経営者、行政、そして地域コミュニティの連携が不可欠です。