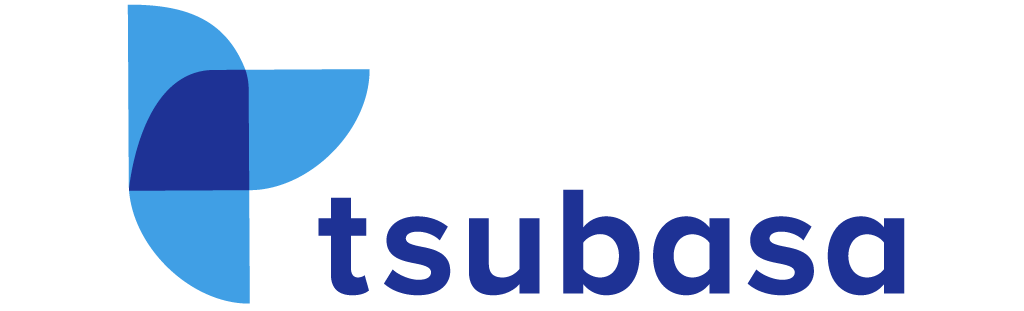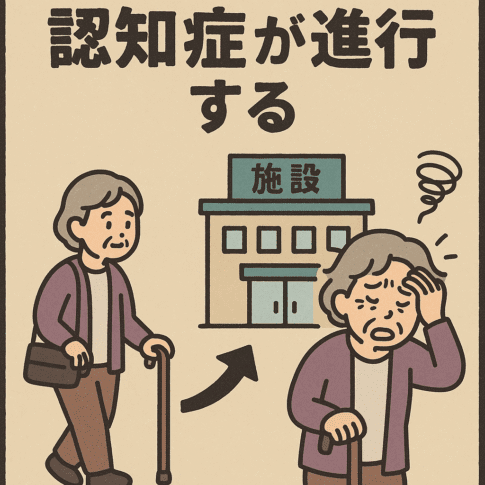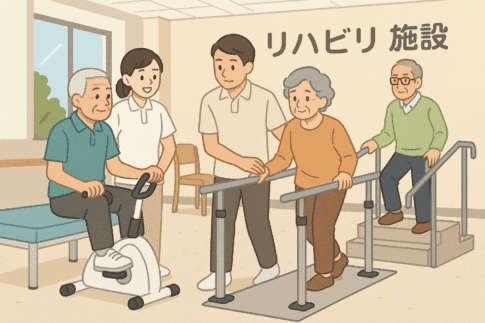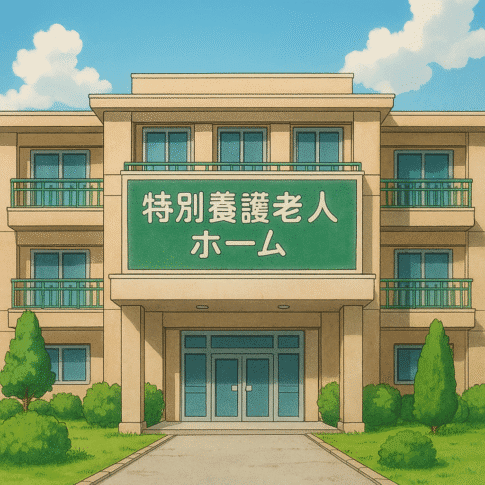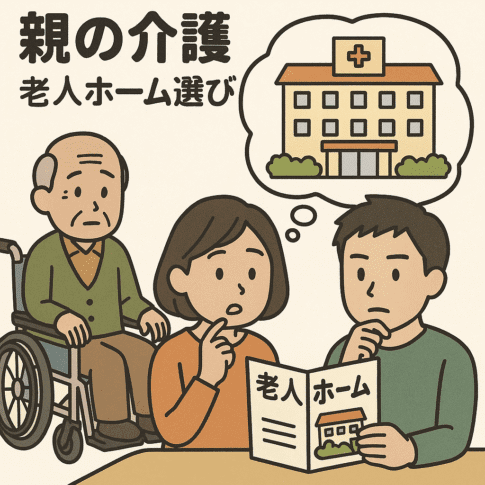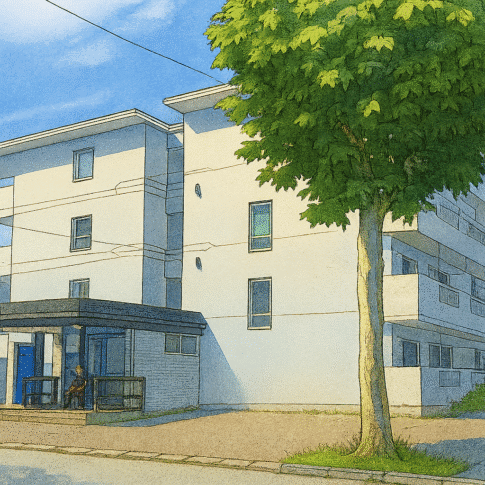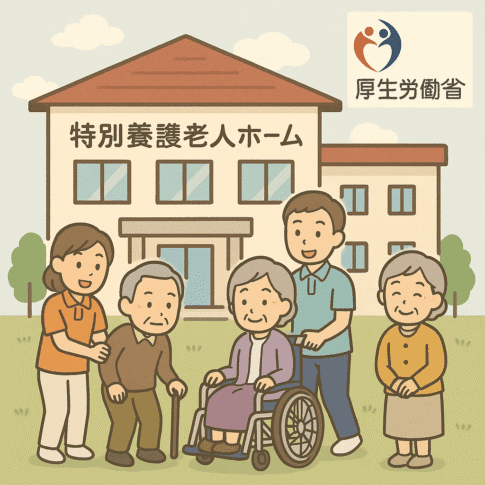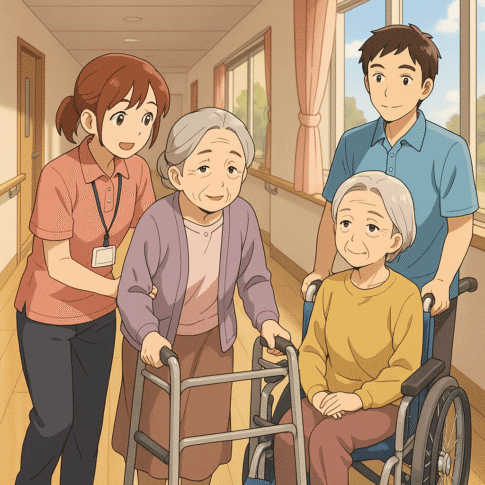近年、高齢者のがん治療をめぐり「医療費の壁」が深刻化しています。
政府が検討する高額療養費制度の上限引き上げが実施されれば、多くの患者が「治療継続の断念」を迫られる可能性が浮上。
「金銭的理由で命の選択をしなければならないのか」——現場から届く悲痛な声を基に、制度変更がもたらすリスクを徹底解説します。本記事は、朝日新聞(2025年1月28日)の記事をもとに作成しています。
Contents
「月13万円超」の負担増で治療継続が困難に? 高齢者が直面する現実
厚生労働省の試算によると、2027年には中間所得層の自己負担限度額が現行比5.8万円増の月13.8万円に達します。
これは高齢者世帯の平均的な光熱費・食費の合計額(約12万円)を上回る数字。
夫の収入だけでは治療費と生活費の両立が不可能です」(乳がん患者・40代女性)
さらに、あるアンケートでは患者の62%が「負担増で治療継続困難」と回答。
特に問題視されているのが「長期投薬が必要な分子標的薬」です。
- 例)乳がん治療薬「パルボシクリブ」:月額約35万円(3割負担で10.5万円)
- 高額療養費適用時:現行上限4.4万円 → 改定後6.2万円(試算)
その結果、「1年で21万円以上の負担増」が発生すれば、貯金の切り崩しや借金が避けられません。
特に、年金生活者や単身世帯ほど影響が深刻化する構図が浮かび上がっています。
「治療あきらめるのか」患者の声から見える3つの危機
全国がん患者団体連合会が集めた3623件の声から、具体的なリスクを整理しました。
危機1:世代間格差の拡大
まず、若年層と異なり、高齢者は収入増加の見込みがほぼありません。「高齢者の医療費」はより生活を圧迫します。
そのため、「定年後も治療費を捻出できるのか」という不安が就労意欲を低下させる悪循環が発生しています。
危機2:家族への負担転嫁
次に、「子どもの学費を削ってまで治療を続けるべきか」(50代男性)といった声が突出。
さらに、約40%の家族が「経済的ストレスで関係が悪化した」と回答しています。
危機3:地域医療の崩壊
地方では都市部に比べ、医療機関の選択肢が限られます。
負担増で通院を断念する患者が増えれば、地域病院の経営悪化に拍車がかかる懸念が指摘されています。
専門家が提言する「負担軽減」への具体的解決策
社会保障審議会委員・山田太郎氏(仮名)は次の対策を提案します。
対策1:所得区分の細分化
現行の6区分から10区分へ拡大し、低所得層の負担増幅を抑制。
特に年金収入のみの世帯に特化した救済枠の創設が急務です。
対策2:長期治療者向け優遇制度
5年以上治療を継続する患者に対し、負担上限を現行水準に固定する「ロック制度」を導入。
イギリスやドイツでは既に同様の制度が機能しています。
対策3:民間保険との連動
公的保険でカバーできない部分を補完するため、保険会社と連携した「がん治療特化プラン」の開発を推進。
70歳以上の加入制限緩和が鍵となります。
最後に ~医療費は「個人の問題」ではない~
「高齢者の医療費」の問題は、超高齢社会の縮図です。
今回の制度見直しをきっかけに、私たちが考えるべきは「治療を諦めない社会」の設計。
患者の声に耳を傾け、世代を超えた対話を深めることが、持続可能な医療制度への第一歩となります。
「命の値段は決められない」
ある肺がん患者の言葉が、全てを物語っています。