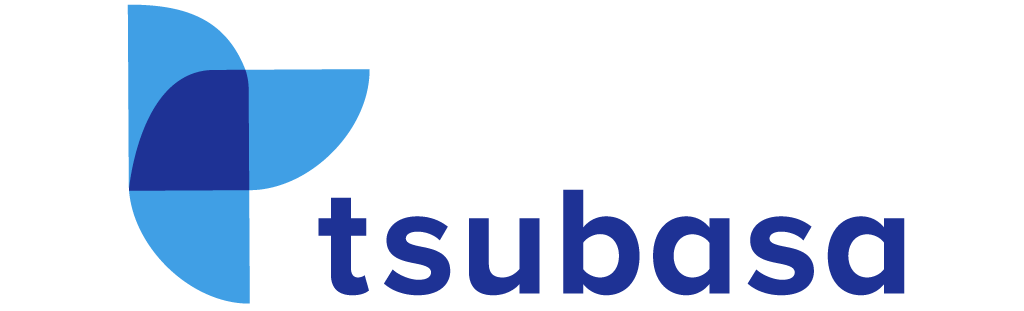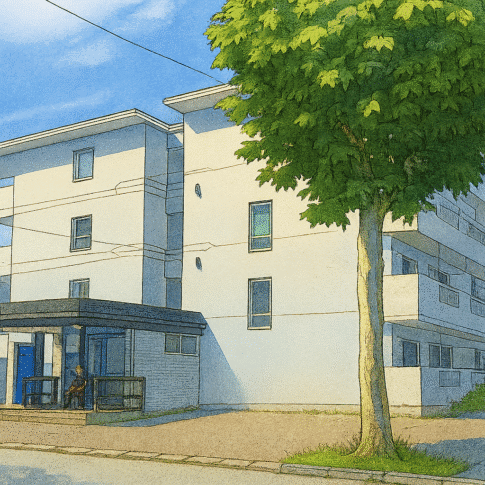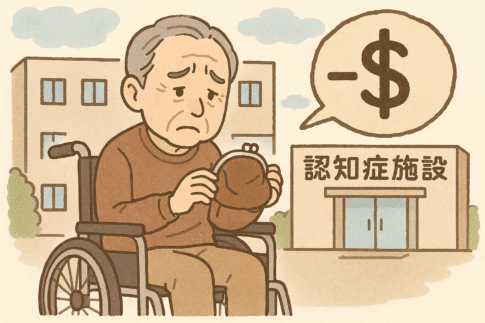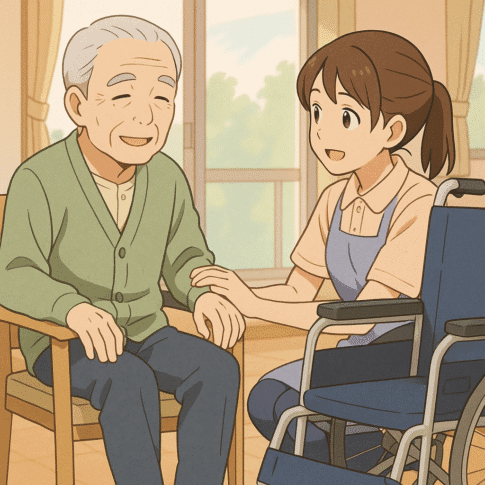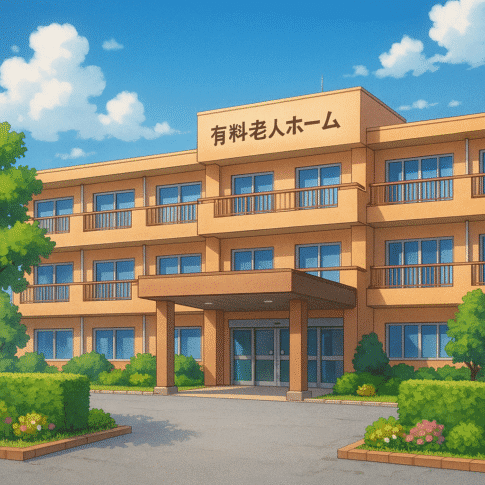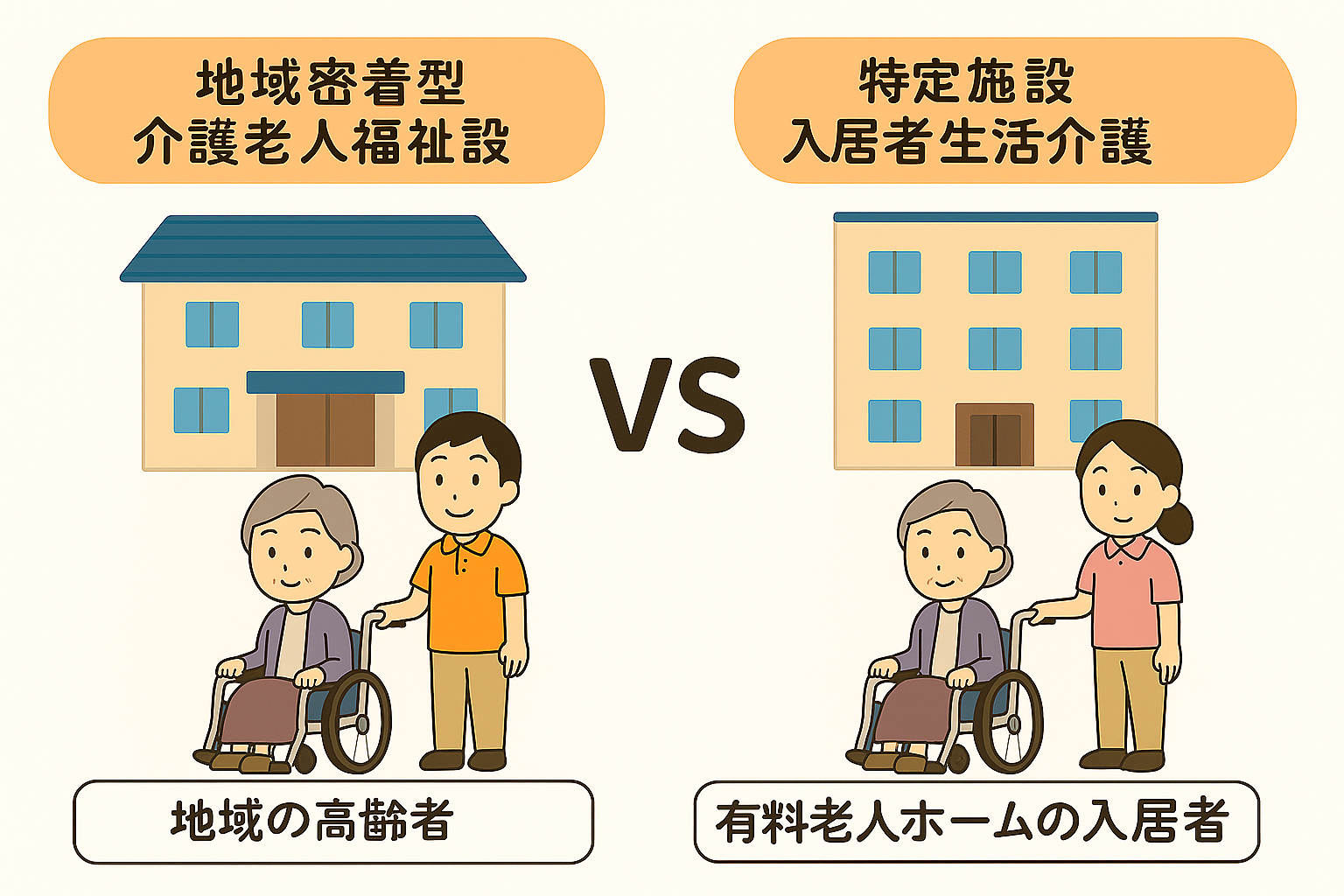厚生労働省が2025年度の公的年金支給額を1.9%引き上げると発表しました。
一見すると3年連続の増額は喜ばしいニュースです。しかし、実は「物価上昇率を下回るため、実質的な目減り」が発生しています。
高齢者の年金に関するこの矛盾の背景にある「マクロ経済スライド」の仕組みや、具体的な受給額の変化を分かりやすく解説します。本記事は、時事通信社(2025年1月24日)の記事をもとに作成しています。
Contents
2025年度:高齢者の年金受給額の具体的な数字
厚生労働省が発表した2025年度の年金額は以下の通りです。
- 国民年金(満額):月額 69,308円(前年度比+1,308円)
- 厚生年金(夫婦モデル世帯):月額 232,784円(前年度比+4,412円)
40年間保険料を納めた場合の基準額で、国民年金は3年連続の増額改定となりました。
しかし、物価上昇率(2.7%)や賃金上昇率(2.3%)と比較すると、高齢者の年金の増加幅が小さいです。そのため、実質的な購買力は低下しています。
なぜ増額なのに高齢者の年金は「実質目減り」なのか?
鍵は「マクロ経済スライド」という制度にあります。
▼ マクロ経済スライドの仕組み
- 年金財政の安定化を目的に、物価や賃金の上昇率から一定率を差し引いて支給額を調整
- 2025年度は賃金上昇率(2.3%)から0.4%を差し引き、高齢者の年金の改定率を1.9%に抑制
▼ 数字で見る「目減り」の実態
| 指標 | 上昇率 |
|---|---|
| 物価(2024年) | 2.7% |
| 賃金(過去3年平均) | 2.3% |
| 年金改定率 | 1.9% |
物価上昇率(2.7%)-年金改定率(1.9%)=実質0.8%の目減り。
つまり、月6万円の年金受給者がいると仮定すると、年間で約5,760円分の購買力が失われる計算になります。
専門家が指摘する「隠れたメリット」
「実質マイナス」と報じられる一方で、定期預金金利との比較では有利との指摘もあります。
- 主要銀行の1年定期預金金利:年1.0%前後
- 年金の名目増加率:1.9%
物価上昇率(2.7%)を完全にカバーできなくても、預金よりも増加率が高い点は評価できるでしょう。
ただし、高齢者の約8割が「食品価格の上昇が生活を圧迫」と回答しており、現実的な家計への影響は深刻です。
今後の課題:年金制度は持続可能か?
日本の年金制度は、少子高齢化と労働人口減少という構造的問題に直面しています。
▼ 高齢者の年金で懸念されるポイント
- マクロ経済スライドの長期化:3年連続発動で、将来的な受給額の伸び悩みが予測
- 保険料負担の増加:2025年度の国民年金保険料は月17,510円(前年度比+530円)
- 世代間格差:現役世代の負担増と高齢者の受給額抑制のバランスが課題
高齢者が今すべき対策3選
- 副収入の確保:在宅ワークやシニア向けアルバイトで収入源を多様化
- 支出管理の見直し:光熱費や通信費の節約プランを検討
- 年金以外の資産形成:iDeCoやつみたてNISAを活用した長期積立
まとめ:増額の裏側にある「現実」を理解しよう
2025年度の高齢者の年金に関する改定は、「名目上の増加」と「実質的な目減り」が共存する複雑な結果でした47。
制度の仕組みを正しく理解し、個人でできる対策を早めに講じることが重要です。
今後の動向に注目しつつ、「年金だけに依存しない老後設計」を心掛けましょう。
※数値データは厚生労働省および総務省の公表資料に基づきます。
参考リンク
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00019.html