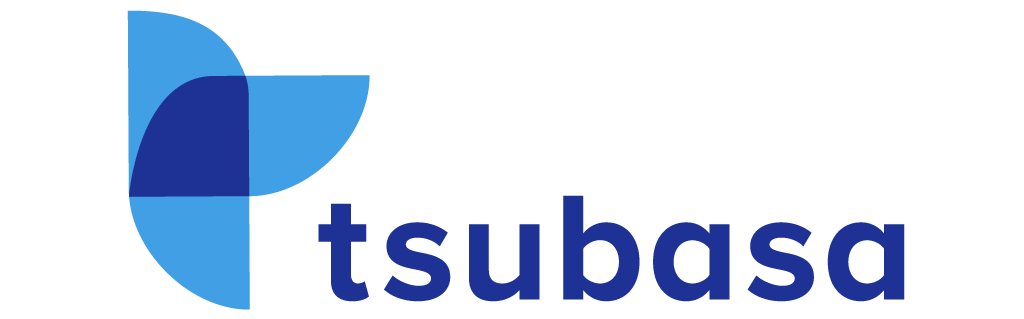高齢化社会が進む中で、在宅医療・介護の重要性が高まっており、訪問看護は重要な役割を担っています。特に、訪問看護指示書は、質の高い訪問看護サービスを受けるために欠かせません。この記事では、訪問看護指示書、特に「特別訪問看護指示書」について詳しく解説していきます。
訪問看護指示書とは?
訪問看護指示書とは、医師が患者の病状や必要な看護内容を具体的に指示し、訪問看護ステーションに提出する書類です。そして、この指示書に基づいて、訪問看護師は医療的なケアや日常生活の支援をします。
訪問看護指示書には、大きく分けて以下の2種類があります。
| 指示書の種類 | 説明 | 発行条件 |
|---|---|---|
| 訪問看護指示書 | 定期的な訪問看護を行う際に必要な指示書。 | 病状が安定しており、定期的な訪問看護が必要と医師が判断した場合 |
| 特別訪問看護指示書 | 病状が不安定な場合など、より頻回の訪問看護が必要な際に発行される指示書。 | 気管カニューレを使用している、真皮を越えた褥瘡がある、その他、病状が不安定で頻回の訪問看護が必要と医師が判断した場合 |
特別訪問看護指示書は、患者が在宅でより手厚い看護を受けられるよう、訪問看護の回数を増やすことができる指示書です。具体的には、以下のような場合に発行されます。
特別訪問看護指示書の発行条件
- 気管カニューレを使用している
- 真皮を越えた褥瘡がある
- その他、病状が不安定で頻回の訪問看護が必要と医師が判断した場合
従来、上記の特定の症状・状態の患者にのみ発行が認められていました。 しかし、近年では、がん末期や難治性潰瘍など、頻回の訪問看護を必要とするケースが増加しています。そのため、対象疾患の拡大が求められています。 また、気管カニューレ使用または真皮を越えた褥瘡がある場合は月に2回まで発行できます。しかしながら、それ以外の場合は月に1回、期間は14日間のみとなります。
特別訪問看護指示書の内容と発行手続き
特別訪問看護指示書には、以下の内容が記載されます。
- 患者の氏名、住所、生年月日などの基本情報
- 診断名、病状、既往歴などの医療情報
- 必要な訪問看護の内容(医療処置、観察、指導など)
- 訪問看護の頻度、期間
- その他、医師が必要と判断した事項
発行手続きは、以下の通りです。
- 患者または家族が医師に特別訪問看護指示書の発行を依頼する。
- 医師が患者の状態を診察し、必要性を判断する。
- 必要と判断された場合、医師が特別訪問看護指示書を作成。訪問看護ステーションに提出する。
特別訪問看護指示書の対象者と利用条件
対象者は、原則として、以下の条件を満たす必要があります。
- 訪問看護を必要とする病状であること
- 居宅において療養生活を送っていること
- かかりつけ医がいること
具体的なサービス内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 医療処置(点滴、注射、創傷処置、カテーテル管理など)
- 病状観察(体温、脈拍、血圧、呼吸状態などのチェック)
- リハビリテーション(関節可動域訓練、筋力トレーニングなど)
- 日常生活の支援(食事、排泄、入浴などの介助)
- 精神的なサポート
- ターミナルケア
- 家族への介護指導
医療処置や病状観察などは、より頻回に提供されることがあります。
特別訪問看護指示書を利用する際の注意点
利用する際には、以下の点に注意する必要があります。
- 有効期間は限られているため、期間内に必要な手続きを行う。
- 訪問看護の内容や頻度は、患者の病状や状態によって異なる。
- 訪問看護の費用は、健康保険や介護保険の適用を受けることができるが、自己負担が発生する場合もある。
特別訪問看護指示書を取り巻く現状と課題
2021年6月に行われた調査によると、医療機関の53.7%が、頻回の訪問看護を必要とする利用者がいると回答しています。 また、同年10月に行われた調査では、18.4%が、月に2回特別訪問看護指示書を発行できなかったケースがあると回答しています。そのため、現状では、発行要件が厳しく、必要な人が必要な時に利用できないケースがあることが分かります。
特に、がん末期や難治性潰瘍の患者など、現状の制度では十分に対応できないケースが増えてきています。頻回の訪問看護が必要にもかかわらず、月に1回、14日間という制限のために、十分なケアを受けられない患者がいることは深刻な問題です。
なお、今後の展望としては、以下のような点が挙げられます。
- 対象疾患の拡大: がん末期や難治性潰瘍など、頻回の訪問看護を必要とする疾患への対応。
- 発行回数の制限緩和: 必要な回数だけ発行できるようにする。
- 手続きの簡素化: 患者や家族、医療機関の負担を軽減するため、発行手続きを簡素化する。
また、訪問看護療養費実態調査の統計データも利用可能です。
まとめ
特別訪問看護指示書に基づくケアは、在宅医療・介護において重要な役割を担っています。特に、高齢化社会が進む中で、その需要はますます高まっていくと考えられます。しかし、現状では、制度の制限により、必要な人が必要な時に利用できないケースがあることが課題として挙げられます。
今後、対象疾患の拡大や発行回数の制限緩和など、制度の改善が進むことで、より多くの人が、質の高い在宅医療・介護サービスを受けられるようになることが期待されます。